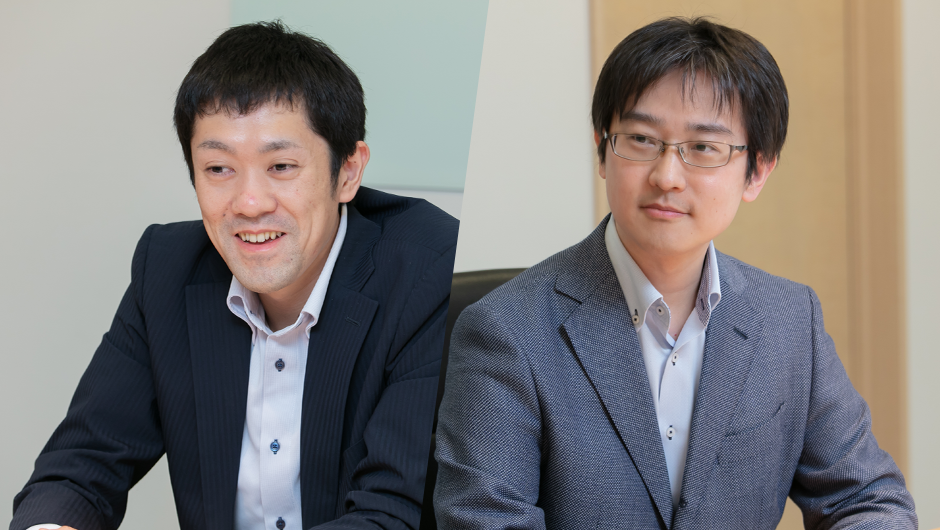
なぜ巨大市場で世界的企業に指名される人材を輩出できるのか?マーケティングコンサルファームの成長環境
マーケティングは専門職で市場価値が高いと考えている方も多いだろう。しかし変化の早いこの時代では「マーケティング職においてもAIや他者に代替されにくい人材を目指す必要がある」。そう語るのはエム・シー・アイ社で活躍する二人だ。世界的製薬企業をはじめ医療・ヘルスケア業界のマーケティングを支援する二人に「求められる価値提供」や「指名される人材になるための環境」について話を伺った。
2021.05.24
株式会社エム・シー・アイ
Y .N 氏・K .F 氏
2021/05/24 (Update: 2022/05/24)

株式会社エム・シー・アイ
interviewee

Y .N 氏
株式会社エム・シー・アイ
マーケティングリサーチ事業部 マネージャー
2014年に新卒でMCIに入社。ヘルスケア業界に特化したマーケティングリサーチコンサルタントとして大手製薬企業のプロジェクトに複数従事。現在は顧客に対する責任者であるプロジェクトリーダーを担うと同時に、後輩メンバーのマネジメントも担当。

K .F 氏
株式会社エム・シー・アイ
人事部門マネージャー
2009年卒。1社目では経営企画室で人事部の立ち上げ、その後上場準備期のベンチャー企業にて採用および上場体制の整備等を経験してMCIに入社。新卒採用以外にも人事領域を広く担当。